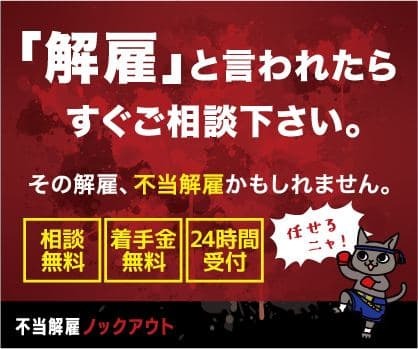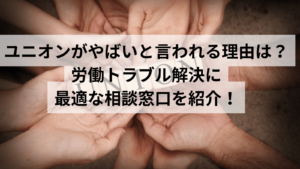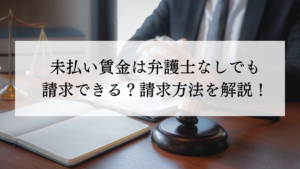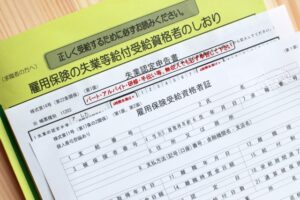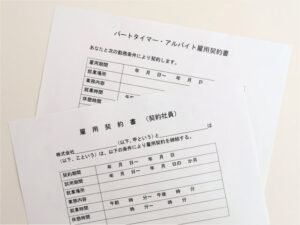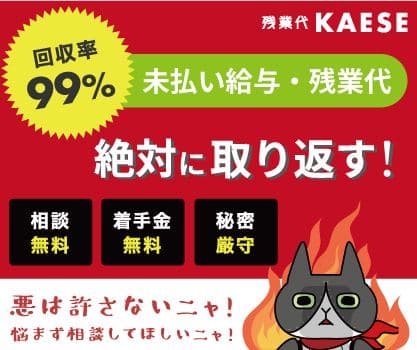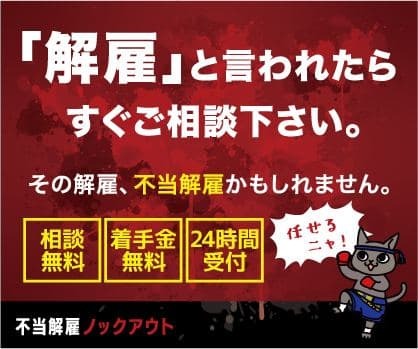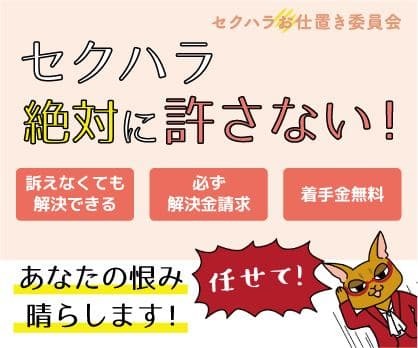本記事にはプロモーションが含まれている場合があります
個人事業主が不当解雇を認められるのは難しい?正しい対処法を徹底解説
突然、継続していた案件の終了を告げられて、不安になっていませんか?
たとえ個人事業主でも、突然の契約終了は不当解雇なのではないかという疑問が生まれるのは、当然の事です。しかし、個人事業主が不当解雇されたと認定されるには、いくつかのハードルがあります。
本記事では、個人事業主に不当解雇が認められるための必要条件を、関連法律をもとにわかりやすく解説します。さらに、個人事業主が急な契約解除をされた時に取るべき対応策や、不当解雇のトラブルに今後遭わないための予防策も紹介するので、ご参照ください。
最後まで読んでいただき、自身を取り巻く環境を正しく理解できて、最適な対応策を見つけましょう。もし、お困りごとがあれば、ねこの手ユニオンまでご連絡ください。
【結論】労働環境によっては個人事業主が不当解雇を認められるケースがある
個人事業主にとって、不当解雇認定のハードルは高いと言えます。個人事業主の仕事は独立した事業者同士の契約に基づくため、労働法の保護は受けられないのが原則です。
しかし、個人事業主に不当解雇が認められるケースは、実際に存在します。労働環境によっては、雇用されて働く労働者と同等の「雇用契約」があると見なされ、労働法の保護を受けられる可能性があるからです。
発注元との業務関係性や、交わした契約内容を精査すれば、不当解雇を勝ち取ることは十分可能です。
個人事業主にとって不当解雇の認定はなぜ難しい?
個人事業主が不当解雇を認められるのが難しい理由は、以下の通りです。
- 個人事業主は労働者ではなく労働法の対象外だから
- 契約形態によって契約解除されやすいから
- 契約自由の原則が適用されるから
それぞれ、具体的に見ていきましょう。
個人事業主は労働者ではなく労働法の対象外だから
個人事業主が不当解雇を認められるのが難しい最大の理由は、法律上「労働者」ではないからです。労働者は労働法によって、解雇の制限や解雇予告、残業代の支払い義務など、様々な権利が守られています。
しかし、個人事業主は、法的には「事業者」として扱われ、発注者と対等な立場にある独立した事業主体と見なされます。そのため、労働基準法などの保護の対象外です。
個人事業主が不当解雇を主張するためには、「労働者性」が認められる労働環境であることを自ら証明しなければなりません。
契約形態によって契約解除されやすいから
個人事業主が発注者と締結する契約には「委任契約」や「準委任契約」、「請負契約」があります。民法651条では「委任契約」「準委任契約」ともに、いつでも契約を解除する自由があると明記されています。
つまり、発注者側はやむを得ない事由がなくても、一方的に契約を終了できる法的根拠があるのです。「請負契約」でも、請負人が仕事を完成しない間であれば、注文者は理由を問わず契約を解除できるので注意が必要です。
ただし、この場合注文者は請負人に対して損害賠償を行う義務が生じます(民法第641条)。
契約自由の原則が適用されるから
民法は「契約自由の原則」を認め、契約当事者における契約の自由を規定するものです。
また、いったん合意した契約条件には、法的拘束力が生じます。
つまり、内容が個人事業主にとって不利な条件であっても、契約書に署名した時点で法的には有効です。
仮に「30日前の予告なしに契約解除できる」「理由なく契約を終了できる」などの条項があれば、裁判所は原則としてこの契約内容を尊重します。契約自由の原則を知らないためか、発注元が提示する契約内容に多くの個人事業主は異議を唱えずに契約を締結しているのが現実です。
個人事業主の不当解雇認定でもっとも重要な「労働者性」とは?
労働者性とは、時間や場所の拘束を受けて指揮命令下で働き、報酬が労務対価として支払われる働き方のことです。個人事業主でも、実質的な労働者性が認められれば、不当解雇と認定される可能性があります。
労働者性が認められるかは、以下の点を精査しましょう。
- 仕事の依頼に対する諾否(だくひ)の自由の有無
- 業務遂行上の指揮監督の有無
- 勤務場所・勤務時間の拘束性の有無
- 報酬の労務対償性の有無
- 事業者性の有無
- 専属性の程度
自身の環境を、労働者性の観点から見直することが大切です。
仕事の依頼に対する諾否(だくひ)の自由の有無
諾否の自由があるかどうかは、労働者性を判断する上での重要な要素の一つです。諾否の自由があるとは、相手から何らかの要望や提案があった際に、承諾するかしないかを自由に決められるということです。
しかし、個人事業主にとって、継続的な発注を途切れさせたくないなどの理由から、事実上依頼を断れないケースは少なくありません。暗黙の圧力があったり、契約書上で受注を強要されていたりする場合は、労働者性が高いと認められます。
実際の裁判例で、依頼を断ることにより不利益を被ったケースについて、諾否の自由が制限されたと判断されているのも好材料です。
業務遂行上の指揮監督の有無
発注者から細かな業務指示を日常的に受けている場合、労働者性が認められる可能性があります。個人事業主にとって自由であるはずの業務の遂行手段を、発注者によって制限されているからです。
具体的には、以下の状況が指揮監督下にあります。
- 仕事の進め方について詳細なマニュアルが存在する
- 日々の業務報告が義務付けられている
- 作業の優先順位を一方的に指定される
具体的な指示や強い拘束力の有無が、重要な観点です。
勤務場所・勤務時間の拘束性の有無
労働者性を判断する基準のひとつに、勤務場所や勤務時間に関する拘束の有無があります。本来、個人事業主は「いつ」「どこで」働くかを自由に決定できる立場にあるはずだからです。
以下の状況は、雇用労働者と同様の拘束を受けていると考えられます。
- 特定の勤務場所への出社義務がある
- 特定の時間帯に勤務する義務がある
- 遅刻や欠勤に対するペナルティがある
たとえリモートワークでも、オンライン上での勤務状況の厳格な管理がある場合は、拘束性があると判断される可能性があります。
報酬の労務対償性の有無
発注者からの報酬が「労働時間」に対して支払われている、つまり労務対償性がある場合は、労働者性が認められる可能性があります。
本来、個人事業主への報酬は「成果物」や「業務の完了」に対して支払われるのが通常だからです。
具体的には、月額固定給や時給制で報酬が支払われている場合などに、労働者性があると判断されます。成果物の完成度や納品の有無にかかわらず、一定期間ごとに決まった金額が支払われる場合も同様です。
交通費や経費の支給方法が会社員と同様の場合も、労働者性を強める根拠になります。
事業者性の有無
逆に、労働者性が低いと判断されて、不当解雇の認定が受けにくくなるケースがあります。
「事業者性」が高い個人事業主ほど、労働者性が低いと判断されるためです。
具体的には、以下の要素が強いと事業者性が高いと判断されます。
- 専門機器を自前で調達している
- 業務遂行中に発生した損害やミスに対して、自己責任で対応しなければならない
- 複数の取引先を持っている
- 自分の名前やブランドで営業活動を行っている
- 確定申告で「事業所得」として申告している
事業者性が高い個人事業主でも、労働者性が認められれば不当解雇として争う余地はあります。
専属性の程度
専属性は労働者性を判断する重要な要素です。
特定のクライアントからの業務が大半を占め、他の仕事を受ける時間的余裕がない場合、労働者性が高まります。週の大半を費やしている、競合他社との取引を禁止されている、常時待機を求められている、などの状況が当てはまります。
また、契約書に「専属」「専任」といった文言がある場合や、暗黙の了解として他社との取引に制限がかけられている場合も同様です。
個人事業主が不当解雇された時に取るべき対応策は?
もし不当解雇であることが明らかな場合は、フリーランス新法と民法に基づき、以下の対応策を取ることをおすすめします。
- 契約内容と解除理由の確認
- 契約条件の再交渉を提案
- 未払い報酬の請求
- キャンセル料・損害賠償の請求
※フリーランス新法(特定受託事業者の適正な取引の推進に関する法律)とは
フリーランスの労働環境を整備するために2024年に施行された法律で、以下の規定があります。
契約内容と解除理由の確認
突然の契約解除に直面した際にまず行うことは、契約書の詳細な確認です。契約書には通常、解除条件や予告期間、違約金などについての規定が設けられています。
記載の条項にもとづいて、発注者側が契約上の義務を履行しているかを正確に判断しましょう。特に確認すべき点は、以下の通りです。
- 契約解除の予告期間(30日前通知など)
- 解除可能な事由(特定の条件下でのみ可能であるなど)
- 違約金や損害賠償の規定
もし書面が存在しない場合は、チャットなどの通信記録や口頭での約束など、契約内容を示すあらゆる証拠を収集しましょう。揃えた証拠は、今後の交渉や法的手続きの基盤となる重要な資料です。
その上で、契約を解除する理由を確認しましょう。
可能であれば、書面が残るメールかチャットを送るのがおすすめです。契約条件と解除理由に矛盾がないか、また解除手続きが契約通りかを確認することが、今後の交渉の重要な基盤になります。
契約条件の再交渉を提案
突然の契約解除通告でも、いったん落ち着いて再交渉の道を探ってみることは大切です。
これまでの業務成果や専門性をアピールしつつ、発注元が抱いている懸念材料を率直に尋ねてみましょう。
報酬体系の見直し、業務範囲の調整、成果物の質の向上などの提案から、新たな取引が生まれることもあります。双方にとってメリットのある解決策を提示することで、関係修復を目指します。
未払い報酬の請求
契約解除に伴って未払い報酬が発生している場合は、確実に回収するための適切な手続きを取りましょう。
まず、未払い報酬の正確な金額を算出し、請求の根拠となる契約書や業務完了の証拠(納品物や作業報告書など)を整理します。その上で、内容証明郵便による正式な請求書を送付します。内容証明郵便は、いつ、どの内容の文書を相手に送付したかを法的に証明する上で重要です。
請求書には支払期限を明記し、期限を過ぎても支払いがない場合は法的手続きを検討する旨を併記しておきましょう。
キャンセル料・損害賠償の請求
契約を一方的に解除された場合、契約条件に基づいてキャンセル料や損害賠償を請求できる場合があります。効力のある請求を行うには、契約違反の具体的な内容と、生じた損害額の明確な算出が不可欠です。
まず、契約書に記載された違約金条項やキャンセル料の規定を確認します。規定がない場合でも、民法上の債務不履行による損害賠償請求は可能です。
損害額に算定できるのは、失った報酬だけではありません。当該契約のために断った他の仕事の機会損失、投資した時間や資源のコストなども含みます。
続いて、チャット履歴や業務指示書など一方的な解除を証明する資料を保全しましょう。できれば専門家の協力を得て、民法上の債務不履行や不法行為に基づく請求が可能か検討しましょう。
示談交渉が難航する場合は、内容証明郵便による請求を行い、法的措置を取る意思を明確にします。最終的には、少額訴訟や調停など法的手続きへの移行も視野に入れておきましょう。
今後のトラブルを防ぐための予防策
今後のトラブルを防ぐための予防策として、適切な契約書作成と必要なリスク管理について解説します。
- 契約書に重要条項を盛り込む
- クライアントを複数つくる
- クライアントの満足度を上げる動きをする
- 第三者機関に相談する
起こり得る問題を日頃から想定しておけば、不当解雇によるトラブルもある程度防げます。
契約書に重要条項を盛り込む
契約書にあらかじめ重要条項を盛り込んでおくことが、急な契約トラブルを有利かつスムーズに解決するためのポイントです。
解除条件を明確化する
契約書には、どの条件で契約解除が認められるのかを具体的かつ明確に記載しましょう。
曖昧な表現はできるだけ避け、期限や回数などを数値化して客観的に判断できることが重要です。また、災害や病気など、責任を負えない状況でも安全に契約を終了できる条件を明確にしておきましょう。
予告期間と違約金を設定する
契約解除に予告期間を定めることは、個人事業主を守る重要な防御策です。可能であれば3ヶ月程度の予告期間を設けることで、次の案件を探す時間的余裕が生まれます。
さらに、正当な理由なく契約解除された場合の違約金についても明記すると効果的です。交渉力が弱くなりがちな個人事業主の立場を守り、クライアントにも契約継続の重要性を認識させる効果が期待できます。
クライアントを複数つくる
個人事業主にとって、特定のクライアントへの依存は大きなリスクです。収入源が複数あれば、そのうちの1社から契約解除があっても、安定して事業を継続できます。
どの取引先も、総収入の30%を超えないバランスが理想的です。多様な業界・規模のクライアントとの取引は、特定の業界の浮き沈みに依存しないメリットも生みます。
また、継続的な案件と短期的な案件をバランスよく組み合わせるのも、収入の安定性を確保するコツです。
クライアントの満足度を上げる動きをする
契約解除を防ぐ最も効果的な方法は、クライアントからの高い評価を維持することです。
納品物だけでなく、案件が依頼されるプロセスも重視し、クライアントが抱える課題の本質的解決を心がけましょう。期待値のギャップを防ぐために定期的なヒアリングを行い、小さな不満が積み重ならないようにすることも重要です。
さらに、少し多めのサービス提供を行ったり、付加価値の提供を心がけたりすることで、代替不可能な関係性を目指します。
良好な信頼関係があれば、多少の問題が発生しても契約解除にはつながりません。
第三者機関に相談する
個人事業主が解決困難な不当解雇トラブルに直面した場合は、専門的な知見を持つ第三者機関への相談が最も効果的です。
業界特有の慣行を踏まえた専門的なアドバイスが期待でき、感情的になりがちな当事者間の交渉をスムーズにする橋渡し役になります。
不当解雇の悩みは外部機関に相談する
ひとりで不当解雇に悩む個人事業主にとって、相談できる外部機関は心強い存在です。ねこの手ユニオンなら、不当解雇に悩む個人事業主の相談にじっくりと乗ってくれるのでおすすめです。
おすすめの理由を詳しく解説します。
- 個人事業主でも相談できる
- 相談から裁判まで一括して代行してくれる
- 着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
個人事業主でも相談できる
個人事業主一人ひとりは弱いため、組織を相手に交渉するのは困難です。しかし、企業との交渉経験豊富な労働組合なら、対等な交渉が可能です。
ねこの手ユニオンのサポートがあれば、個人事業主でも対等な立場で企業と交渉できます。
相談から裁判まで一括して代行してくれる
ねこの手ユニオンでは、弁護士、社会保険労務士、行政書士などの法律の専門家が運営に携わっています。
相談から裁判まで一括代行が可能なのが特長です。
不当解雇について直接対応ができない場合であっても、弁護士を紹介しているので安心です。
着手金無料で完全成果報酬だから安心できる
ねこの手ユニオンは完全成果報酬を採用しているので、着手金・相談料などは必要ありません。
無事に解決できたときに、解決金の3割を支払う仕組みなので、安心です。
その他の外部相談機関
その他にも、個人事業主が不当解雇に悩んだ時に相談できる外部機関があります。
- 労働基準監督署
- 弁護士
- 総合労働相談コーナー
- フリーランス・トラブル110番
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法などの労働関係法規の順守を監督する国の機関です。
労働条件や安全衛生などの違反に関する申告を受け付け、必要に応じて事業主に対する監督指導や是正勧告を行います。
個人事業主であっても、実態として「労働者性」が認められる場合は相談できます。
ただし、民事上の紛争解決機関ではないため、解雇の効力そのものを判断する権限はありません。
弁護士
弁護士は、契約書の解釈や実質的な労働者性の有無など、法的観点から解雇の不当性を評価してくれます。交渉が難航した場合には損害賠償請求訴訟の提起も可能です。
労働問題に強い弁護士を選ぶことで、解決の可能性が高まります。
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や労働基準監督署内に設置された無料相談窓口です。
個人事業主と発注者間の契約トラブルについても、労働者性が認められるケースについては相談に応じてくれます。専門の相談員が対応するので、法的な観点からアドバイスを得られるのも特長です。
必要に応じて労働局内にある「紛争調整委員会」によるあっせんも利用可能です。あっせんは裁判よりも短期間・低コストで解決を図れる制度で、円満解決の可能性が高まります。
フリーランス・トラブル110番
フリーランス・トラブル110番は、厚生労働省の委託を受けた弁護士が相談に乗ってくれる相談窓口です。個人事業主やフリーランス特有の契約トラブルに特化しており、匿名での問い合わせも可能です。
一般の労働相談では対応しきれないフリーランス特有の問題について、専門知識を持つ相談員がアドバイスを提供します。
労働環境を確認し不当解雇と闘おう
個人で事業を行っていると、さまざまな問題に直面します。なかでも、契約の継続は収入に直結する重要な課題です。誠実に業務に取り組んできたにも関わらず、突然契約を中断されるのは、誰でも納得が行かないものです。
発注者の依頼に対し、熱心に応えてきた個人事業主であればあるほど、労働者性が認められ不当解雇の可能性は高まります。自身の労働環境を客観的に分析し、個人事業主としての権利と地位を守る闘いに臨みましょう。
本記事が健全な事業活動の一助になれば幸いです。